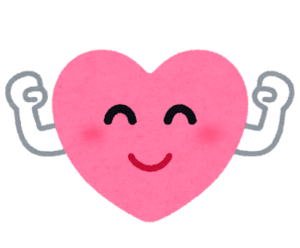2025年10月28日の夕刊に、
<ライフスタイル 働く>ストレスチェック 活用半ば 職場改善へ専門家と連携
という記事が掲載されました。
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、働きやすい職場づくりを進めるために導入された仕組みです。
アンケートを通じてストレスの状況を把握し、必要に応じて医師による面接指導や職場環境の改善につなげることが目的とされています。
しかし記事によると、制度の導入から数年が経過した今も、十分に活用されているとは言いがたい状況です。
高ストレスと判定された従業員のうち、実際に面談を受けているのはわずかで、結果を職場改善へと結びつけられていない企業も多いとのことでした。
一方で、前向きに取り組む企業の事例も紹介されていました。産業医や専門家と連携し、ストレスチェックの結果を分析して具体的な「アクションプラン」を立てたり、従業員が気軽に相談できる「立ち話面談」や保健室での声かけを実践している企業もあります。
こうした取り組みは、従業員が心身の不調を感じたときに早期に相談できる環境づくりに直結しており、信頼関係の構築にもつながっていると感じました。
記事を読んで強く感じたのは、ストレスチェックを「実施すること」が目的化してしまうと、本来の効果が得られないという点です。
形式的に実施しても、結果を放置すれば従業員の信頼を失いかねません。むしろ大切なのは、チェックの結果を丁寧に分析し、組織としてどのように改善していくかを明確にすることだと思います。
また、産業医や保健師といった専門職だけでなく、管理職や同僚など、日常的に関わる人たちが小さな変化に気づけるような風土づくりも欠かせません。
上司からの何気ない声かけや、雑談の中でのコミュニケーションが、従業員の安心感や早期対応につながることも多いと感じます。
ストレスチェック制度は、単なる「義務」ではなく、職場の健康文化を育てるための大切なツールです。
記事にあるような先進的な取り組みを参考にしながら、結果をきちんと“活かす”仕組みをつくることが、今後ますます重要になると思いました。
最終的には、従業員一人ひとりが安心して働ける環境を整えることが、企業の成長にもつながると改めて感じます。
<小松 優佳>